 85式は楊式の宗家 楊露禅が大成したもので、錬丹法の一つとして黄帝内径とか気功と併せて行われ、仙人を目指す道教の太極陰陽思想の意識を内に秘めています。
85式は楊式の宗家 楊露禅が大成したもので、錬丹法の一つとして黄帝内径とか気功と併せて行われ、仙人を目指す道教の太極陰陽思想の意識を内に秘めています。
中国の華僑賢人達の錬金術として伝統的に伝承され、そこから国民体育法として24式や、その他の流派の集大成として48式が生まれ、88式は85式の体育法として現在に至っています。私たちの太極拳の目的は錬丹法としての太極拳であり、太極拳を深く練っていきます。… 続きを読む
 85式は楊式の宗家 楊露禅が大成したもので、錬丹法の一つとして黄帝内径とか気功と併せて行われ、仙人を目指す道教の太極陰陽思想の意識を内に秘めています。
85式は楊式の宗家 楊露禅が大成したもので、錬丹法の一つとして黄帝内径とか気功と併せて行われ、仙人を目指す道教の太極陰陽思想の意識を内に秘めています。
中国の華僑賢人達の錬金術として伝統的に伝承され、そこから国民体育法として24式や、その他の流派の集大成として48式が生まれ、88式は85式の体育法として現在に至っています。私たちの太極拳の目的は錬丹法としての太極拳であり、太極拳を深く練っていきます。… 続きを読む

準備 南を向いて立つ /1.起勢チーシ始まりの型/2.右左野馬分 馬のタテガミを分ける/3.白鶴亮翅 白鶴が翅を広げる/4.左右ロウ膝拗歩 膝を払う5.手揮琵琶 琵琶を抱く/6.左右倒巻肱 肱を巻き込む/7.左攬雀尾 鳥の尾をなでる/8.右攬雀尾 鳥の尾をなでる/9.単鞭 鞭の型/10.雲手 雲を押し出す/11.単鞭 鞭の型/12.高探馬 馬の背から探る/13.右トウ脚 踵で蹴り出す/14.双峰貫耳 … 続きを読む
 套路は、最終的に神=しんという人間の根本的な生命力で動くことを目指します。
套路は、最終的に神=しんという人間の根本的な生命力で動くことを目指します。
武当派ではそのことを、存思(そんし)といいます。
存思(そんし)とはいわゆる瞑想のことですが、仏教などで言われる瞑想とは又違います。
太極拳の源流には坐道といわれるものがありますが、そこでも行われていた瞑想法です。
存思(そんし)は人間の生命の根源、すなわち純粋無邪気な無為なエネルギーに自らを置いている状態のことです。
仏教の禅のように悟りを得るためとか、無念無想とかと又感覚が違い、もっと躍動的でかつ、無為で純粋なものです。生命の根源にあるような根本的な存在で動くのが瞑想太極拳です。… 続きを読む
 海底針は太極拳における裏勢(りせい)=(体の内側を使って抱き込むような勢)を習得する重要な招式です。
海底針は太極拳における裏勢(りせい)=(体の内側を使って抱き込むような勢)を習得する重要な招式です。
双龍拉椀(そうりゅうらわん)は海底針の示意であり、相手の手首の内側を双龍の上あごで、外側を大小の拳頭を下あごでひしぎ噛んで上あごを裏勢にもとづき内側に引き込み、上あごを前側へ押し噛んでいく手法です。
この裏勢がないと、以上の拉勁は発勁とはならないのであり、重要な練習方法となります。
海底針の裏勢は多くの擒拿術に含まれますが、この双龍拉椀は最も基本的な示意なので、単法として相対で練習をします。… 続きを読む
太極拳は円の動きで動くと一般では理解されています。確かに十三勢の四正手(しせいしゅ)は円と曲の勢です。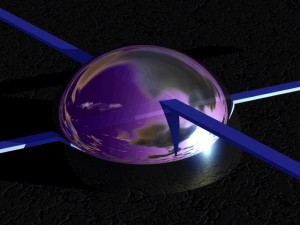
ところが四隅手(しぐうしゅ)は直と伸の勢であり、後は五行の方角で十三勢となっているのです。
四正手は太極拳を聞いたことがある人なら円の柔らかな動きということで理解はできるでしょうが、四隅手は理解しにくいものです。
四正手も四隅手も五行も、相対の武道練習において詳しく学びますが、四隅手の勢を実感できるのは特に拳脚の相対練習になります。… 続きを読む
武当派の楊式太極拳では龍の勢(沾粘纏糸の勢)を多用します。
 双龍採扌厥(そうりゅうさいけつ)・双龍大扌履(そうりゅうだいり)・双龍斜飛(そうりゅうしゃひ)双龍撇身(そうりゅうへいしん)大纏手(だいてんしゅ)や小纏手(しょうてんしゅ)昇龍纏腕(しょうりゅうてんわん)などの太極拳の擒拿術は、龍の勢を実感するのにとても役立ちます。
双龍採扌厥(そうりゅうさいけつ)・双龍大扌履(そうりゅうだいり)・双龍斜飛(そうりゅうしゃひ)双龍撇身(そうりゅうへいしん)大纏手(だいてんしゅ)や小纏手(しょうてんしゅ)昇龍纏腕(しょうりゅうてんわん)などの太極拳の擒拿術は、龍の勢を実感するのにとても役立ちます。
とても大切なことですが、龍の勢は龍脈を通ると言うことです。龍脈は聴勁により感じ取り、入り口からしか入ることができません。そして出口からでることにより、龍の勢による発勁は完成します。… 続きを読む
太極拳は意識で動く?そんなことをしていたら太極拳ではなくなります。
太極拳は無意識で動きます。
無意識とは何でしょうか?
無意識とは意識がないと言うことでしょうか?
実は違うのです。
意識には顕在と、潜在があります。そのどちらも意識なのです。
潜在にある意識が、自分では顕在しないで働くことが最も多く、癖や執着などに現れます。煩悩や見えない雑念なども全てそこにあります。
太極拳で言う、無意識とは完全なる純粋な意識です。無為自然と言います。… 続きを読む
まず結論から言いますが、どちらも良いということです。
どちらでも、おおらかに滔々とした套路が行えるというのが太極拳の向かうところです。
太極拳は、太極といわれるように混沌とした世界を全て融合して和合するものです。
この私たちが生きている実際の毎日の社会そのものも、混沌とした世界です。
よく、音楽を聴いていると心が定まらないし、意識が散乱するので、套路をするときには音楽を聴かない方が良いといわれる場合があります。… 続きを読む
太極拳は道教の理念を武道の中に多く取り入れています。
道教の祖師は老子ですが、彼の「無用の用」という概念は有名です。
例えば、太極拳の套路で、広い公園で大きな大地に立っていますが、大地の内で使っているのは足で踏んでいる部分だけです。だからといって、足が踏んでいる部分だけを残して他が無くなってしまったらどうでしょうか?奈落の底に脱落ですね。このように踏んでいるところは用、踏んでいないところは無用、次に踏んだところが用であり、踏み終えたところが無用に変化するのです。これが太極拳の歩法です。… 続きを読む
この撇身捶を招式という一つの技に分割すると、さっと50ぐらいはあげることができます。
85式の套路には撇身捶が数回出てきますが、その撇身捶を全て違う招式や用法を想定して練習するのが最も太極拳を使えるようになるための効果的な套路練習です。
武当派の流れをくむ王の楊式太極拳は実戦的な徒手武術です。その套路にある撇身捶は基本勢のみを練り上げる基本式です。

王の楊式太極拳にはその撇身捶の基本勢をもって行う多くの招式があります。主に拳脚による攻防が中心です。もちろん把式も多くあります。… 続きを読む